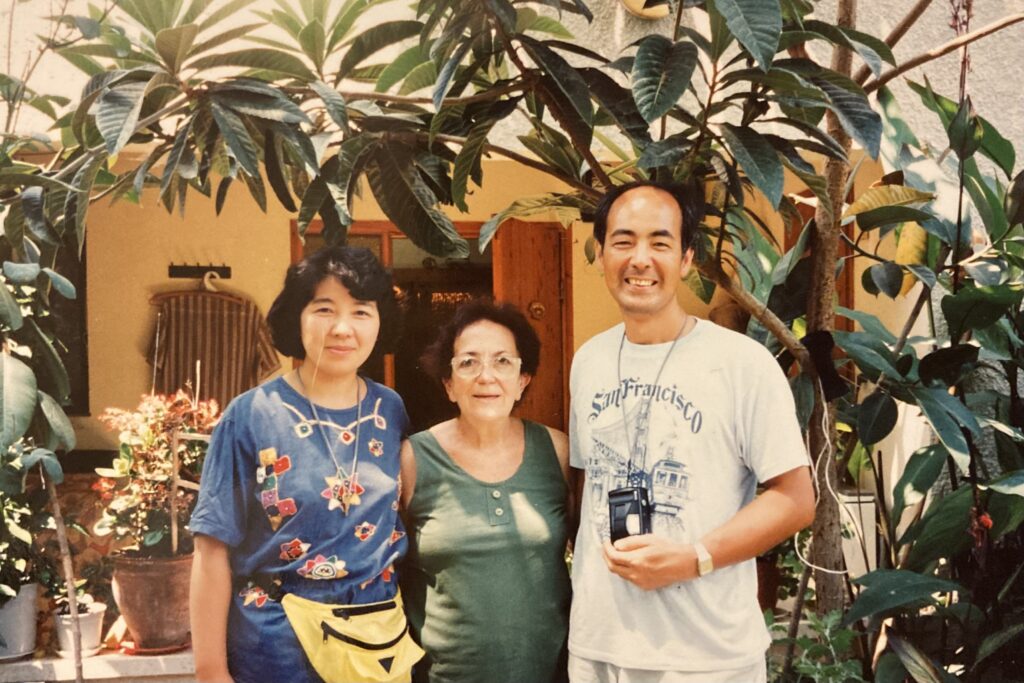いよいよキブツでの労働ヴォランティア生活が始まった。2月28日(月)であった。キブツの朝は早い。5時半には起床しなければならない。夙川教会のSさんから頂いた小さな目覚まし時計が大きな力となってくれた。この時計は6ヶ月の滞在期間中、フルに働いて私の目覚めを助けてくれたのである。
6時前には食堂近くにある駐車場に集合する。マタイ福音書20章のぶどう畑の主人の物語そのままの世界だと思った。2月末の午前6時前は日の出のよほど前で周囲はまだ薄暗い。私たちは古いワゴン車に乗せられて畑に向かう。
今日は私たち5人全員アボカド畑で作業するのである。薄暗く、しかも朝もやのかかったシャロン平野を南に向かっている。このもやは昼になっても晴れることはなく、一日中たちこめていることが多かった。もやに包まれた景色は薄緑色の世界で、とても幻想的である。約5分ほどで畑に着いた。
今朝は雨は降っていなかったがレインコートとブーツを着用した。露などで枝葉が濡れていて、全身がずぶ濡れになってしまうからである。この日は果実の収穫作業であった。